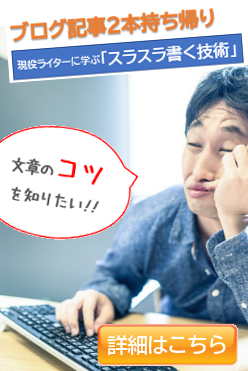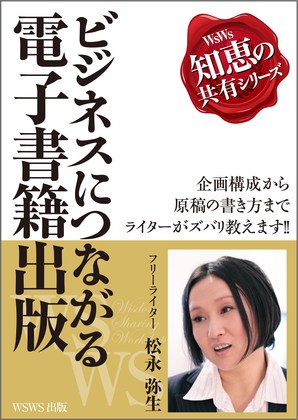テーマ + ターゲット → 切り口
私は、関西 を中心にロボット関連の記事を執筆してきました。
を中心にロボット関連の記事を執筆してきました。
(ちなみに、ロボット系の記事を発表するときは、三月兎のペンネームを使っています。)
関西でロボットに特化したライターが他にいないため、記者会見やロボットコンテストがあるとWEBニュースや専門誌に執筆することがあります。時には公式サイトにも掲載するため、3本の記事を書いたこともありました。もちろん、編集部には複数の媒体に執筆する旨を事前に伝えて、了承を得ています。
そういう話をすると、「取材が一度ですむから、ラクだね」と思われるかもしれません。中には、「原稿を使い回ししているの?」と考える方もいるかもしれません。
言うまでもありませんが、同じ原稿を編集部に納品するわけにはいきません。
私は、出版社から原稿の依頼をいただくまでに、ライターになるための勉強をしたことがありませんでした。身近に先輩として指導をしてくださるライターさんもいませんでした。
だから、複数メディアに記事を執筆する際に、どうやって1つのネタで記事を書き分けたらいいのか、相談する人もいなくて、最初はかなり悩みました。
気づいてしまえば、簡単なことなんですが……。
掲載媒体が異なれば、読者層も違います。
例えば、ロボットコンテストのレポートを書く場合。
WEBメディアであれば、多くの方に読んでいただけます。
「日本人はロボットが好き」と、一般に言われていますが、世間でいう「ロボット好き」とロボットを自作してコンテストに出場する人では、明らかに傾向が違います。
WEBメディアでは、記事によっては一般的なロボット好きの方にも読んでもらうことができます。写真だけでなく動画を掲載できるのも、WEBメディアの強みです。
一方、専門誌はコアなロボット好きの方々が読者です。実際にロボットコンテストに出場している方や研究者がターゲット。
コンテストの結果は、競技会場で知っているはず。自分が出場するロボット大会以外も、WEBニュースや仲間うちの情報で入手しています。
だとしたら、速報や競技結果だけではない部分の情報があれば、読者に喜んでもらえるでしょう。
そう考えて記事を書いていたら、専門誌への原稿はどんどんマニアックになっていきました(笑)
同じ題材であっても、読者が変われば求められる情報も違ってきます。それを常に意識して記事を書いてこれたのは、私にとってよい経験でした。
ライターであれば、ターゲットに向けて記事を書くのは基本ですが、毎回のように記事をかき分ける経験をすることはないでしょう。知らず知らずに、いい訓練をしてきました。
新しい媒体に企画を提案する際に、すぐに連載が決定したのも、テーマとターゲットを意識して、そこから切り口を考える習慣がついていたのが、有効に働いたと考えています。
文章を書くときに、
・何のために書くのか
・誰に読んでもらうのか
・読者が求めている情報は?
といったことを意識するだけでも、反応が変わってきます。
文章というのは、ニュース記事やブログだけではなく、報告書や提案書も含みます。書き出す前に、上記の3点を考えてみてくださいね。
-
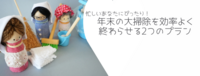 忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。
-
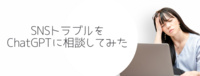 SNSトラブルをChatGPTに相談してみた
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。SNSを使っていると、想
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。SNSを使っていると、想
-
 ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理ADHDの私は、日々のタスク整理と優先順
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理ADHDの私は、日々のタスク整理と優先順
-
 ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です
-
 自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。私が「ア
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。私が「ア

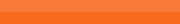

 情報発信に悩んだら、無料で相談してみませんか?
情報発信に悩んだら、無料で相談してみませんか?