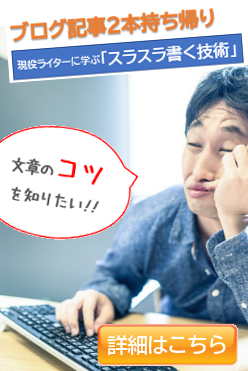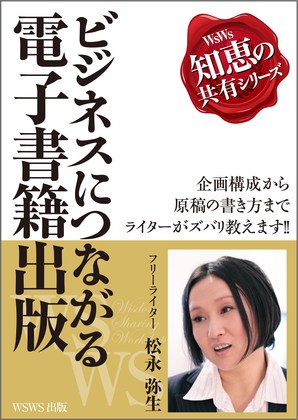痴漢抑止バッジの広報戦略①

こんにちは。経営者のための文章コンサルタント松永弥生です。
今日は、私が代表理事をしている痴漢抑止活動センターが行っている「痴漢抑止バッジプロジェクト」の広報戦略についてお話をいたします。
自分の体験談を事例としてお話するのはおこがましいんですけれども、私が一番密に関わっている広報ですし成功例でもあるので、当時どんなことを考えて行っていたのか。その後の展開等についてもお話ししたら、これから広報を始める方の参考になると思うのでお伝えいたします。
まず「痴漢抑止バッジプロジェクト」とは何か? という話から。
高校入学直後から痴漢に遭っていた女子高校生が、「もう痴漢に遭いたくない!」と考え「痴漢は犯罪です。私は泣き寝入りしません」と書いたカードをカバンに付けて電車登校をしたところ、被害に遭わなくなったのです。
バッジを考案したのが、私の友人の娘さんです。私は、友人からこの話を聞いたときに非常に驚いて、お嬢さんがたった1人でこのバッチをつけずにいられるよう、誰もが痴漢にあわなくなるよう、このアイデアを広げたいと思いました。
大きめの手作りカードを付けやすいデザインの缶バッジにして、普及させることを提案しました。
このとき、私の中にあったのは、
・缶バッチを集める資金をクラウドファンディングで募る。
・デザインコンテストを実施して、バッチのデザインを募る。
特別に深い考えがあったわけではなく、クラウドファンディングを成功するためには、口コミで情報を広げなきゃいけない。私のネットワークだけで情報発信するのは難しいから、デザインコンテストを併催すれば、コンテストに参加してくれるデザイナーさん達も一緒に口コミで広めてくれるだろう。
それぐらいの単純なアイデアでした。
ところが、クラウドファンディングの母体になってくれたfavvoの方が、「そういう企画ならクラウドワークスさんでコンテストをすればいいんじゃないか?」と提案してくださり、クラウドワークスの方をご紹介いただきました。
私の話を聞いた担当者が、非常に共感してくださり、クラウドワークスから全面バックアップがいただけることになりました。
社会的意義のある企画だと、なんと東京のオフィスで記者会見まで開いてくれたのです。
私はクラウドファンディングを始めてから、少しずつ口コミで広げていくのんびりした戦略しか考えていなかったので、いきなり話が大きくなったことに驚きました。
結果として、記者会見に参加くださったライターさんの記事がYahoo! トップニュースに掲載されたおかげで、それからクラウドファンディングが終了するまで、途切れずに取材がありました。
またクラウドワークスのコンテストの応募点数も、2週間で400点を超え、過去に類を見ないほどの数だと驚かれました。もちろん、クラウドファンディングも大成功で、目標額の4倍を超えるご支援が集まりました。
成功要因はありました。
女子高校生考案の痴漢対策グッズというストーリー性。
当時まだ目新しかったクラウドファンディングとクラウドソーシングを活用し、社会貢献活動を始めたという点。
計算していたわけではありませんが、話題になるフォーマットにピッタリと当てはまっていました。けれど私は、この企画が成功した根本的な理由はそうしたフォーマットではないと思っています。
当時の私は、どのようにしたら話題が広がるかと言うのは漠然としか考えてませんでしたが、メディアの目にとまれば、必ず取り上げていただける自信がありました。
問題は、どうやってメディアに届けるか? だったのですが、その点をクラウドワークスさんのご協力でクリアできました。
2015年当時は、まだ痴漢や性暴力に対して声を上げる女性は少なかったです、ネット上で声をあげれば、被害に遭っている女性がバッシングされるのが常でした。その中で、顔出しこそしないものの女子高校生が、手記で被害を語り、手作りのバッジを発表し、そのアイデアを社会に広げる活動は、非常に大きなインパクトのある取り組みだったのです。
私もライターとして仕事をしているので、これがどれだけ社会的意義があることなのかは分かっていました。だからこそ私は、自分が経験のない分野だけれども、この缶バッジを何が何でも世の中に広げたい、1人でも多くの女性にこんなやり方で痴漢を防げると伝えたいと言う強い気持ちがありました。
広報する上で一番大事なのは、その企画や商品やサービスに対する思い入れだと思います。
思いがあるから「どうすれば話題が広がるのか?」と仕掛けを考えます。私が、クラウドファンディングと、デザインコンテストを同時開催しようと決めたように。
アイデアが面白ければ、思いがけない協力者がうまれ、そこから広がることもあります。
次回、その後の広報戦略についてお話します。
| 項目 | 所要時間(分) | 文字数 |
| キーワード出し | 6 | |
| 音声入力 | 11 | 1873 |
| 推敲・修正 | 26 | 1922 |
| 校正(2回) | 9 | 1971 |
| タイトル画作成 | 10 | |
| アップロード | 5 | 1984 |
| 計 | 67分 | 1984 |
-
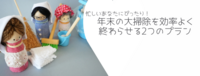 忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。
-
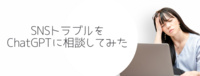 SNSトラブルをChatGPTに相談してみた
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。SNSを使っていると、想
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。SNSを使っていると、想
-
 ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理ADHDの私は、日々のタスク整理と優先順
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理ADHDの私は、日々のタスク整理と優先順
-
 ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です
-
 自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。私が「ア
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。私が「ア

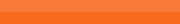
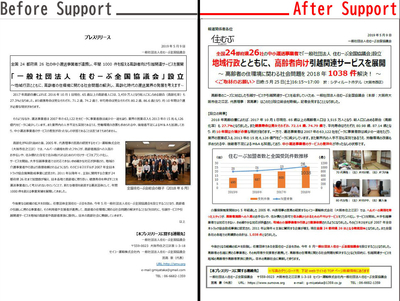
 情報発信に悩んだら、無料で相談してみませんか?
情報発信に悩んだら、無料で相談してみませんか?