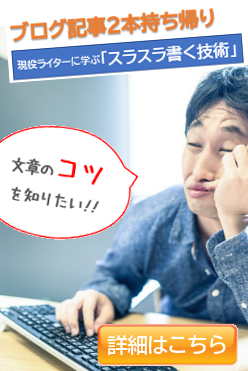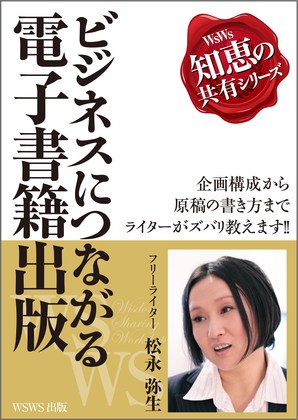「絶対、正しい日本語」なんてない!?
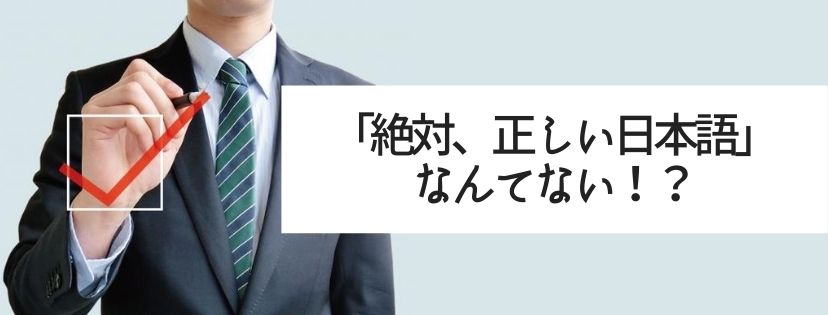
こんにちは。経営者のための文章コンサルタント松永弥生です。
今日は「絶対に、正しい日本語、なんてない!?」についてお話をします。
「文章を書くのが苦手」という人の中に、「ちゃんと書けない」「これでいいのか、不安」と悩んでいるケースがあります。
もちろん、文章の構文が正しいに越したことはありません。主語と述語の関係がおかしかったり、て・に・を・はが間違っていたりすると読みにくくなるし、誤解を招くこともあります。
だけど、私たちは日常で会話をするときに、そこまで正しい日本語を使っていません。だから、いざ、文章を書こうとしたときに、ふと迷ってしまうことが多いのだと思います。
細かな表現や言い回しなど「口語と文語は違う」のを漠然と知っているから「これでいいのかなぁ?」と悩みますよね。
基本的なところは、押さえておいた方がよいけれど、全てにおいて正しい日本語があるわけではないと私は考えています。
どうして、そう考えるようになったかと言うと、言葉の使い方は時代とともに変わると知ったからです。
私は、小学校の時に国語の授業で「“全然”は、否定とともに使う副詞」と教わりました。
「全然、面白い」という言い方は間違いで、「全然、面白くない」が正しい。全然を使ったら、そのあとには否定がこなければならない。
学校の授業で教わったのだから、これが正しい用法だと思いますよね?
だけど、私は、日常の中で「全然、面白い」とか「全然 OKです!」みたいな言い回しをしてしまいます。
書き言葉の中では気をつけるようにしているんですけれど、日常の中では、つい出ます。
そんな風に、私なりに注意して“全然”を使っていたのですが、実は、“全然”を、否定形とともに使うルールは戦後に広がった話だと、大人になってから知りました。明治時代の文学には、“全然”を肯定とともに使ってる表現も多いというのです。
「言葉は生き物だなぁ」と思ったきっかけです。
文章講座の中で、言葉が生き物である事例として、
「心が折れるという表現は、昭和の頃はしませんでしたよね?」
と参加者に話しかけたら、とても驚いた声で「えっ!? だったら、なんて言っていたんですか?」と質問され、一瞬、言葉に詰まってしまいした。
私もとっさに、昭和の頃になんて表現していたのか思い浮かばなかったんです。
「そういえば、なんて言ってたっけ?」と考え込んでしまうくらいに、「心が折れる」という表現が当たり前になってしまっているんですね。
ちなみに昔は、気持ちがくじけるとか、やる気をなくすとか、そういう言い方をしていました。
「心が折れる」は1990年代にスポーツ選手の間で使われ、2000年になって一般的に広まったそうです。2006年には大辞林(三省堂)の辞書にも登録されました。
2018年には「ググる」や「バズる」、「沼」といったネットスラングも高校生向け国語辞典「三省堂現代新国語辞典(第6版)」に掲載されています。
流行の言い回しの全てが残っていくわけではないけれど、言葉は私たちの生活とともに変化していきます。
だからあまり「正しい日本語」にこだわりすぎてはいけない。 と、私は思うのです。
もちろん、誰に何を伝えるのかを考えた上で、適切な言葉を選ぶのは必要です。
自分が、なるべく正しい日本語、伝わりやすい言葉を話したり、書いたりする心がけは大切です。だけど、他の人が自分と違う基準で言葉を使っているときに、わざわざそれを咎めなくてもいい。
そう考えておけば、自分の書いている文章に対しても「不安になった時は、念のために調べてみよう」と思えるようになるのではないでしょうか。
| 項目 | 所要時間(分) | 文字数 |
| キーワード出し | 20 | |
| 音声入力 | 14 | 1289 |
| 推敲・修正 | 15 | |
| 校正(2回) | 8 | 1485 |
| タイトル画作成 | 10 | |
| アップロード | 5 | 1503 |
| 計 | 72分 | 1503 |
-
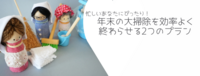 忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。
-
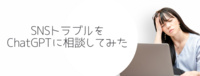 SNSトラブルをChatGPTに相談してみた
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。SNSを使っていると、想
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。SNSを使っていると、想
-
 ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理ADHDの私は、日々のタスク整理と優先順
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理ADHDの私は、日々のタスク整理と優先順
-
 ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です
-
 自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。私が「ア
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。私が「ア

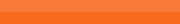

 情報発信に悩んだら、無料で相談してみませんか?
情報発信に悩んだら、無料で相談してみませんか?