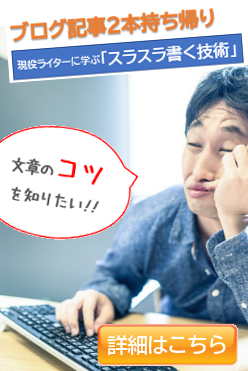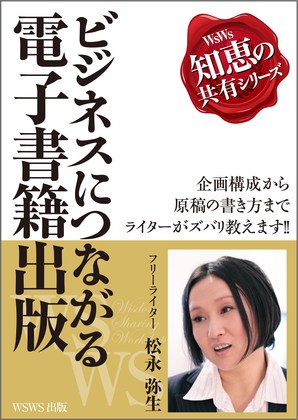痴漢抑止バッジプロジェクトの広報戦略③

こんにちは。経営者のための文章コンサルタント松永弥生です。
今日は「痴漢抑止バッジプロジェクトの広報戦略③」についてお話をします。
マスコミは第1回目のコンテストやイベントは記事にしてくれますが、2回目以降は、なかなか記事にしてもらえません。「初物にはニュース性があるが、2回目以降にはない」と判断されがちだからです。
ですから、2016年度の第2回痴漢抑止バッジデザインコンテストは、何が前回と違うのか、新しい取り組みをアピールすることに力を注ぎました。
まず、コンテストの応募対象者を学生に限定しました。
これは、痴漢抑止バッジを考案したのが高校生であり、被害に遭っているのも中高校生が多いこと。そうした現状を、デザインを学ぶ学生たちに解決してほしいという思いがあったからです。
それに伴い審査員も高校生にお願いすることにしました。
審査には、2016年3月に、無料配布イベントに参加してくれた高校に打診しご協力を得ました。
それ以外にも2次審査を一般投票とし、ウェブ投票だけではなくあべのハルカス ウォールギャラリーを借りて展示する。そして表彰式もあべのハルカスのステージで行うなど、一般を巻き込むような形にしました。
単に痴漢抑止バッジのデザインを学生から募るだけではなく、社会全体を巻き込む姿勢を明確にしたのです。
ギャラリー展示を公民館ではなく商業施設を使うことにしたのは、企画としても意義があります。
公民館での開催は、痴漢問題に関心を持った人しか訪れてくれません。でも、天王寺駅直結の百貨店あべのハルカスのウォールギャラリーなら、買い物に来た親子連れが通りすがりに目を止めてくれます。
表彰式には、大阪府鉄道警察隊のご協力を得て痴漢抑止に関する寸劇をあべのハルカスのステージでしてもらいました。
どれも企画の意義を明確すると同時に、メディアにも訴求できる一石二鳥のアイディアでした。
コンテスト開始のキックオフ
高校生による審査
ウォールギャラリーの二次審査
表彰式
受賞作品の製品化
と1回のコンテストで、記事になるチャンスが5回ある。
広報として、コストパフォーマンスの良いコンテンツになりました。
マスコミにアピールする場合「絵になる」場面があると非常に有利です。取材がしやすくなるからです。その点も抜かりなく意識して企画を立てました。
これから広報活動を始める方の参考になれば幸いです。
| 項目 | 所要時間(分) | 文字数 |
| キーワード出し | 8 | |
| 音声入力 | 5 | 892 |
| 推敲・修正 | 11 | 981 |
| 校正(2回) | 6 | 982 |
| タイトル画作成 | 5 | |
| アップロード | 4 | 1001 |
| 計 | 39分 | 1001 |
-
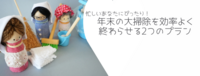 忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン
忙しいあなたにぴったり!年末の大掃除を効率よく終わらせる2つのプラン#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。
-
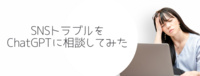 SNSトラブルをChatGPTに相談してみた
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。SNSを使っていると、想
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた
SNSトラブルをChatGPTに相談してみた#暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。SNSを使っていると、想
-
 ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理ADHDの私は、日々のタスク整理と優先順
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理
ADHDでも仕事の段取りがラクラク!ChatGPTで優先順位を自動整理ADHDの私は、日々のタスク整理と優先順
-
 ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと
ADHD・ASDの特性と私の新しいリズム:生成AIとの会話で気づいたこと暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です
-
 自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。私が「ア
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション
自分を信じる力が湧く!ChatGPTで作る朝のアファメーション暮らしを助けるAIガイド 松永弥生です。私が「ア

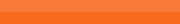
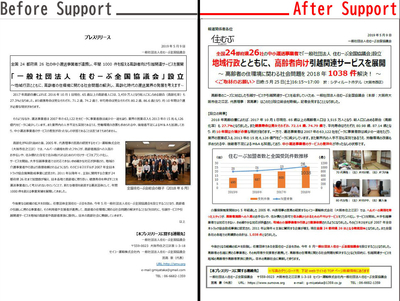
 情報発信に悩んだら、無料で相談してみませんか?
情報発信に悩んだら、無料で相談してみませんか?